痙縮(ボツリヌス・ITB)外来
痙縮は、脳卒中、頭部外傷、脳性麻痺、脊髄疾患、痙性対麻痺などの疾患に起因する症状で、リハビリの大きな障害となりADLの回復を妨げ、また、ADLを低下させていきます。このリハビリ障害因子である痙縮に対する最も効果的な治療法であるボツリヌス療法とバクロフェン髄注療法(Intrathecal baclofen therapy:ITB療法)を両者とも当院では、行っています。局所の痙縮が、ボツリヌス療法で、より広範な痙縮がITB療法の適応になります。これらの治療法の使い分けが大切ですが、この両治療法を組み合わせて治療することも可能です。以下、ボツリヌス療法とITB療法について説明します。
手足の筋肉の緊張をやわらげる! ーボツリヌス治療とはー
私たちが腕を曲げ伸ばしするとき、脳からの命令が脊髄を通って運動神経に伝わります。脳卒中、頭部外傷、脊髄損傷など、脳や脊髄が損傷した後遺症や、脳性麻痺などによる「痙縮(手足の筋肉がつっぱる、緊張や反射が強くて固い、動かしにくいなどの症状)」がおこると、日常生活に支障をきたします。また、痙縮の症状を長い間放っておくと、筋肉が固まってさらに関節の運動が制限される「拘縮」という症状につながることもあります。
ボツリヌス治療とは、まず服薬から開始して効果がみられない場合に、筋肉の緊張をやわらげる薬剤(A型ボツリヌス)を注射し、筋肉につながる神経の働きを抑えて痙縮をやわらげます。手術に比べて患者さんの心身的な負担が少なく、日常生活の改善や介助量の軽減につながります。
注射の効果は通常3~4カ月程度で、繰り返し注射することになります。効果が続く期間は個人差があるので、医師と相談しながら次の計画を立てていく必要があります。
また、超音波検査などを使って正確な投与部位の位置を確認することで、深部の筋肉にも適切に薬剤を注入することができ、同じ薬剤の用量でも高い効果を示すことが可能です。そのためにも、専門の医師による診療が大切です。

手足の筋肉の緊張、つっぱりによって起こること
- 手が握ったまま開かない、手の指、手首が曲がって伸びない
- 足のかかとがあがる、膝が内側に向いたり、曲がって伸びない
- 肩やひじが固まって動かない、脇や股関節が開かない など

ボツリヌス治療で期待できる効果の可能性
- 手や指の動作がしやすくなる(つかむ、はなすなど)
- 歩きやすくなる、座りやすくなる、リハビリがしやすくなる
- 手のひらやわきの下などが洗いやすくなり、清潔を保てる
- 着替えやおむつの交換が楽になり、介護の負担が軽くなる
- 痙縮による痛みがやわらぐ
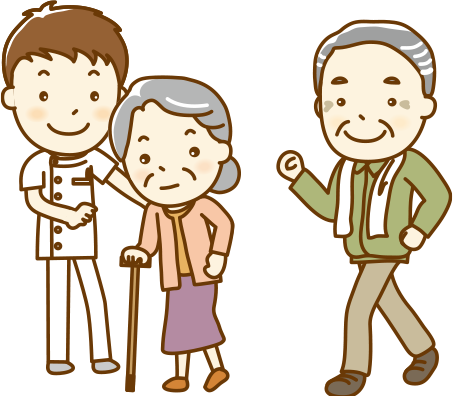
関節が柔らかくなることで、日常生活動作や寝たきりの方の介護がしやすくなります。
バクロフェン髄注療法(ITB療法)
体内植込み型ポンプシステム
バクロフェン髄注療法とは、バクロフェンというお薬を作用部位である脊髄の周囲へ直接投与することにより、痙縮をやわらげる治療です。この治療では、患者さんの状態に応じてお薬の量を調節することにより痙縮をコントロールすることができます。痙縮をやわらげることで、日常生活の活動の幅を広げたり、生活を豊かにすることを目的としています。
治療の流れ
- スクリーニング(効果の確認):治療を始めるにあたっては、ポンプの植込み手術を行う前にこの薬が患者さんに効果があるかどうかを確認するためのスクリーニングを行います。ポンプを植込む前に、このお薬が患者さんに効果があるかどうか、腰から少量のお薬を注射して効果を確認します。
- ポンプ、カテーテルの植込み手術:お薬の効果を確認できたら、ポンプ、カテーテルの植込み手術を行います。下肢のみの痙縮の軽減を図る場合は、下位胸椎レベルに
カテ先を設置し(図A)、上肢も含めて上下肢ともに痙縮の軽減を図る場合は、上位胸椎から頚椎レベルにカテ先を設置することにより(図B)、痙縮の効果範囲をコントロールすることもできます。

図A(カテ先は、下位胸椎レベル) 
図B(カテ先は、上位胸椎レベル) - お薬の調節や補充(定期通院):ポンプに入れたお薬がなくなる前に、お薬を補充します(リフィル)。症状にあわせてお薬の量を調節します。この治療法は、術後、きめの細やかなお薬の調節ができることが最大の特徴です。
当院におけるこれまでの実績
ポンプ植込み術:8例
リフィルのための通院:11例
外来診療日
外来診療日のページをご確認ください。
